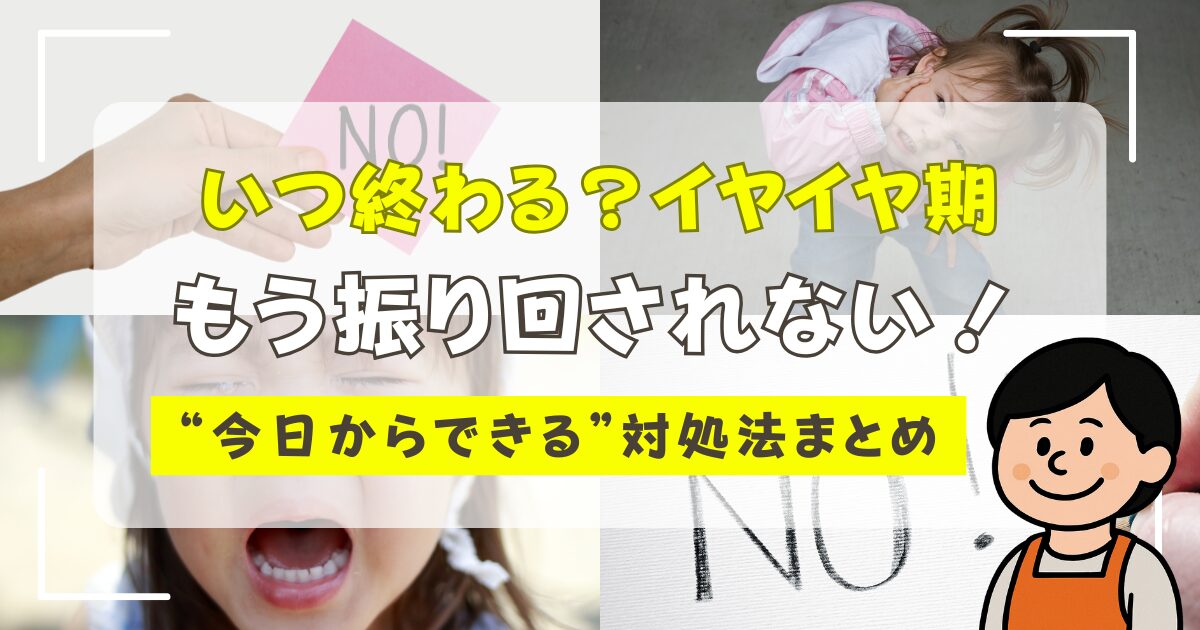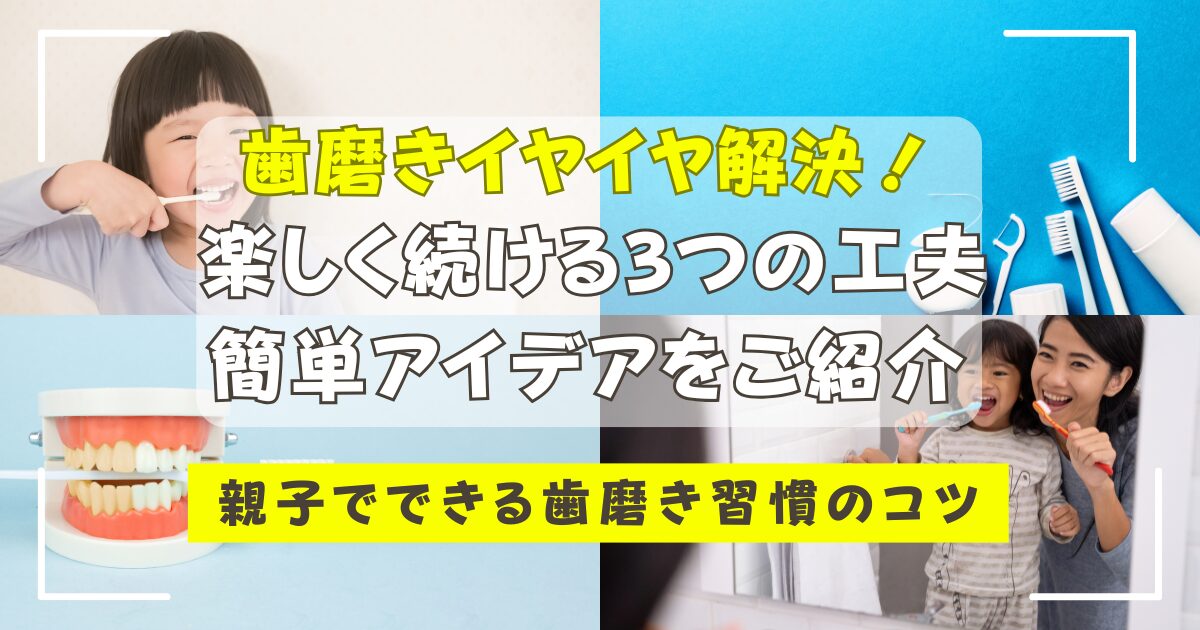「毎日“イヤ!”ばっかりで、もう限界…」そんなママパパへ。
2歳のイヤイヤ期っていつ終わるの?どう関わったらいい?
保育士ママが“今日からできるヒント”をお届けします。
 なおみ先生
なおみ先生こんにちは、なおみ先生です!
保育士としての経験や、子育ての日々から感じたことをお届けしています。
この記事では、保育士としてたくさんの子どもと関わってきた経験と、ママとしてリアルに向き合ってきた体験を交えて、「今日からできる!7つの対処法」をお届けします。
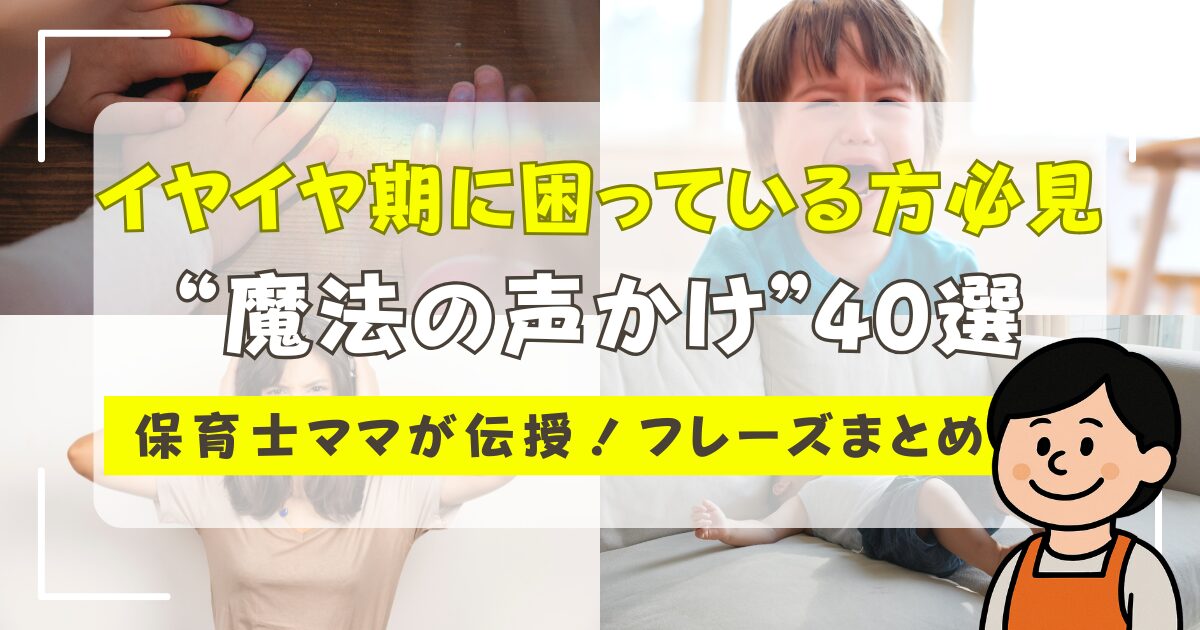
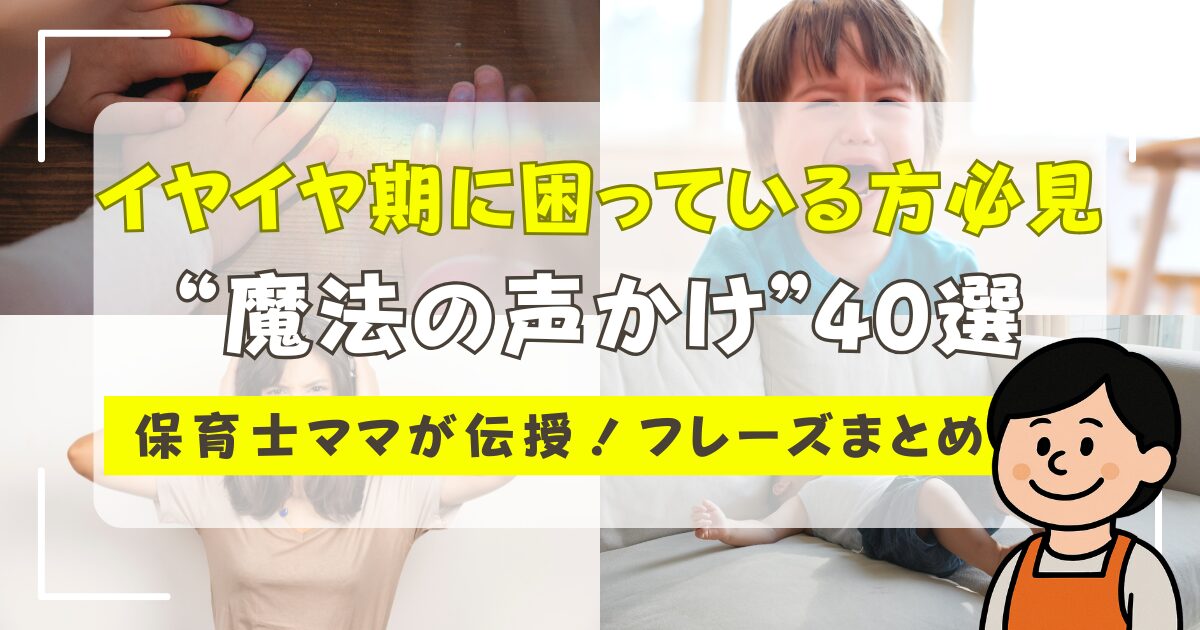
イヤイヤ期ってなに?脳の発達と関係アリ
「なんでこんなに“イヤ”ばっかり言うの?」と思ってしまうイヤイヤ期。
でも実はこれ、子どもが“自分”という存在に気づき始めた証なんです。
2歳前後の子どもは、前頭前野(感情のコントロールや我慢をつかさどる脳の部分)が未発達。
そのため、気持ちをうまく言葉で伝えられず、“イヤ!”と叫んだり、泣き叫んだりする形で出やすいのです。
つまり、イヤイヤ期とは:
- 自分の意思が芽生えた証
- 感情をコントロールする練習の時期
- 「伝えたいのにうまくできない」もどかしさが爆発する時期
という、心の成長のど真ん中にいるサインなんです。
つまり、“イヤ!”というのは、自我の芽生え=立派な成長サイン。
それを理解してあげることが、イヤイヤ期をうまく乗り越える第一歩になります。
でも親は振り回されがち…そこで必要なのが、理解+工夫です!
【保育士が教える】2歳イヤイヤ期の特徴とは?


2歳ごろの子どもって、本当に“予想外”の連続。
昨日まで平気だったことが、急に「イヤ!」になるのがこの時期の特徴です。
保育現場でも、よく見かけるイヤイヤ行動にはこんなものがあります:
- 気に入らないとその場に寝転んで動かない
- 「これがいい!」と急に主張し始める(でもすぐ変わる)
- ママじゃなきゃイヤ、パパじゃなきゃイヤ…と“推し”が日替わり
- 時と場所を問わずに“今!?”というタイミングで爆発
特に多いのが、日常生活のルーティンに関わるイヤイヤです。
たとえば:
- おきがえイヤイヤ(服が気に入らない/靴下を拒否)
- 歯みがきイヤイヤ(口を開けない/歯ブラシを拒否)
- ごはんイヤイヤ(“これじゃない”と怒る/食べること自体を拒否)
- おでかけイヤイヤ(玄関で固まる/靴を履かない)
これらのイヤイヤには、
“自分で決めたい”
“注目してほしい”
“不快感を伝えたい”
など、ちゃんと理由があることも。
つまり、子どもの行動の裏には“まだ言葉にできない気持ち”が詰まっているんです。
そこを理解して関わるだけで、イヤイヤの嵐も少しずつ落ち着いていきます。
イヤイヤが激しいときのNG対応3つ
子どもが全力で「イヤー!」と叫んでいるとき、ついこっちも感情的になりがち。
でもその瞬間の対応が、イヤイヤ期の行動パターンを大きく左右することもあります。



私自身も、上の子のときに「やめて!」「もう知らない!」と声を荒げてしまった経験が何度もありました。
でも、あとで自己嫌悪に襲われるんですよね…🥲
そんな経験を経て、今は避けるようにしている“NG対応”がこちら。
❌「もういい加減にして!」と怒鳴る
→ 子どもは“大人の感情”に敏感。
怒鳴られることで「自分はダメなんだ」と思い込んでしまうことも。
❌「好きにしなさい!」と突き放す
→ 放任と尊重は違います。突き放されると、子どもは“どうしたらいいか”が分からなくなります。
❌「〇〇ちゃんはできるのに」と比較
→ 他人との比較は、自己肯定感を大きく傷つける原因に。
💡代わりに心がけたいのは:
- 「気持ちは分かるよ」とまず共感する
- 選択肢を提示して“選ばせる”
- 一緒に考える姿勢を見せる
この3つ。
完璧じゃなくていいけど、“受け止める姿勢”を意識するだけで、親子の空気は大きく変わります。
今日からできる!イヤイヤ期の乗り越え方7選
子どもによって、イヤイヤの“クセ”や“ツボ”は違います。だからこそ、いろんな工夫を試してみることが大切。
ここでは、保育士&ママとして実際に効果があった7つの関わり方をご紹介します。
子どもの気持ちに共感する
「そっか、着たくなかったんだね」「今はまだやりたくなかったんだね」と、まずは“受け止め”から。
特に2歳は、気持ちをうまく言葉にできない時期。
気持ちを代弁してもらえるだけで、ふっと落ち着くことも多いです。
我が家では、泣き叫ぶ息子に「いやだったんだね〜」と膝に座らせてひと呼吸置くことで、切り替えられる場面が増えました。
選択肢を用意する
「赤い服と青い服、どっちにする?」など、2択で選ばせると“自分で決めた感”がうまれてスムーズに進むことがあります。
このときのポイントは、“どちらを選んでも親は困らない選択肢”にしておくこと。
うちでは、靴下選びでよくこの手を使います(笑)
楽しいルーティンをつくる
決まった順番や儀式のような“安心できる流れ”があると、子どもは次の行動に移りやすくなります。
たとえば我が家では、「お風呂の前にこの歌」「歯みがきの前にこの絵本」を固定ルーティンにすることで、スムーズに切り替えられるように。
ルーティン=予測可能な安心感、なんです。
小さな達成感を積み重ねる
「できた!」「ひとりでできた!」という小さな成功体験は、次の行動への意欲につながります。
息子には「ズボン履けたね!」「口を開けて磨けたね!」と、行動ごとに具体的に褒めるようにしています。
ごほうびやスタンプもいいけれど、何より“ママの笑顔”が一番のごほうびなんですよね☺️
ポジティブな言葉をたくさん使う
「ありがとう」「助かったよ」「うれしいな」
など、日常の中で前向きな言葉を意識的に増やすと、子ども自身の言葉づかいにも表れてきます。
先日、息子が「ママ、さっき助けてくれてありがとう」って…泣きそうになりました🥹
親の“構え”をゆるくする
完璧を求めすぎず、「ま、いっか」の気持ちでやり過ごすことも大事。
「長靴はいてるけど晴れてるしな…でもご機嫌ならOK!」
「朝ごはんバナナだけ?でも食べたからヨシ!」
“気にしない力”も、親のスキルのひとつです。
どうしてもダメなときは“遊びに変える”
やらせたいことを「遊び」に変換すると、うまく乗ってくれることがあります。
・歯みがき→「歯医者さんごっこ」
・手洗い→「泡でおにぎり作り」
・お片づけ→「おもちゃ列車発車しま〜す!」
ごっこ遊びや競争風にすると、ぐんとやる気がアップする子が多いですよ✨
育児の「あるある」が止まらない毎日に、べあるがそっとバンザイ。
寝かしつけ成功も、立ち食いごはんも、全部がんばった証。
今日も私たちはえらい!
▶︎ べあるのLINEスタンプを見る
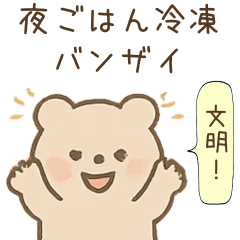
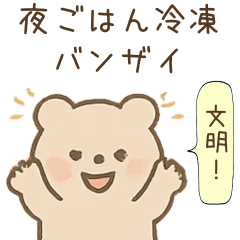
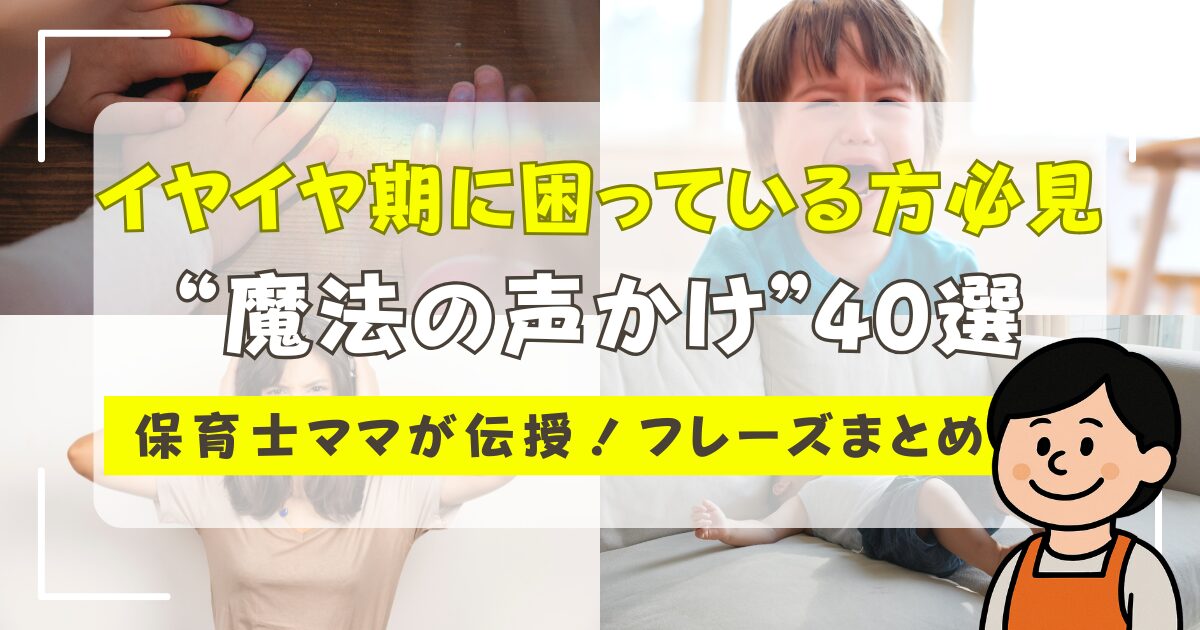
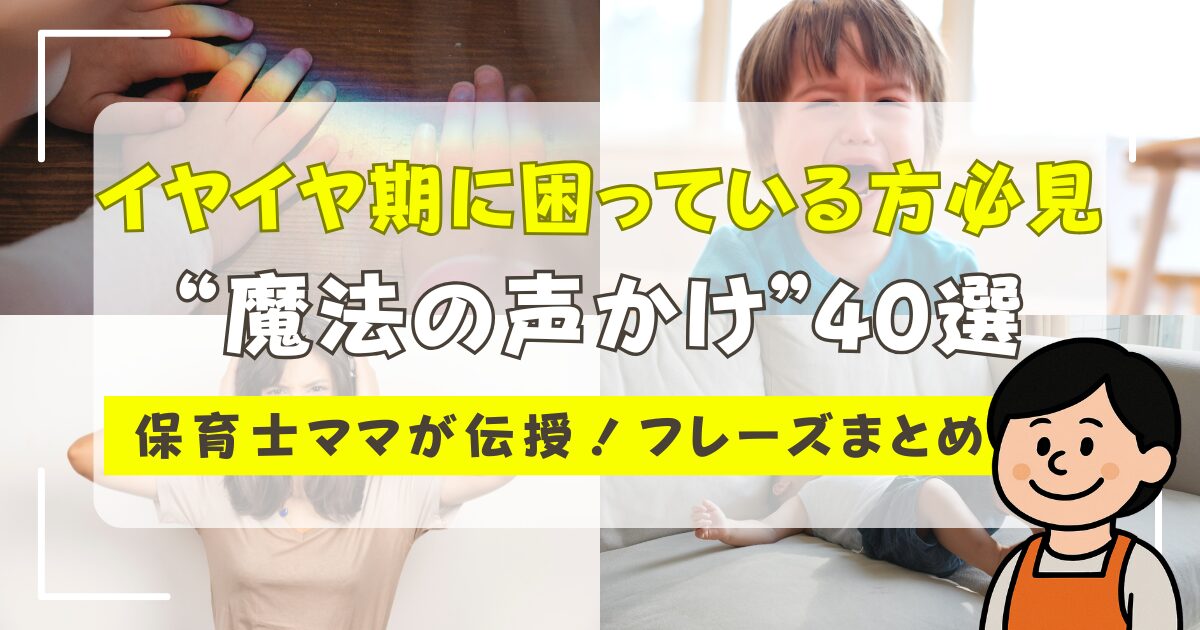
親がしんどいときはどうする?リセットのコツ
子どものイヤイヤに日々向き合っていると、知らず知らずのうちに親の心がすり減っていきます。
「泣き声を聞くだけでイライラ…」
「何もしてないのに涙が出てきた」
──そんな日があっても、ぜんぶOK。
- 1人になれる時間を5分でもつくる
トイレの中、ベランダで深呼吸、車の中でコーヒー。
どこでもOK。
とにかく“ひとり”の時間があるだけで、心が整いやすくなります。 - 「今は嵐の中なんだ」と客観視する
「この子はわざと困らせようとしてるんじゃない。心の嵐を起こしてる最中なんだ」
と思えると、ほんの少し冷静になれます。 - 思いを吐き出す場をもつ
育児日記やSNS、友達とのLINEでもOK。
「今日めっちゃ疲れた」「泣かれすぎて無理」って書くだけで、気持ちがスッと軽くなることも。 - 自分にも“ありがとう”を言う
「今日もよくがんばったね」と、鏡に向かって言うの、ほんとにおすすめです。
保育士として、ママとして思うのは──
イヤイヤ期を“しのぐ”のではなく、“一緒にやりすごす”感覚が大事だということ。



感情のコントロールが難しいときもありますよね!
でも、それを「子どもと一緒に練習してる」と思えると、ちょっと心が軽くなりますよ。
べあるから、がんばるママ・パパへ
「イヤイヤ〜って泣かれて、こっちが泣きたくなる日もあるよね…」
そんなときは、ふぅ〜っと深呼吸して、
☕️ 1杯のコーヒーで、心に“よゆう”をチャージしよ!



がんばってるあなた、今日もえらいっ!
極・馨 -Gokkoh-(カフェインレスコーヒー)
妊娠、授乳中でも安心して楽しめる本格フレーバー。
カフェイン0.1%未満・化学薬品不使用・余韻のある香りとコク深い味わい。
香りで甘さを感じる、がんばるママの“ごほうび”コーヒーです🌸
イヤイヤ期、実際いつ終わる?
一般的には、1歳半〜2歳ごろにイヤイヤ期が始まり、2歳半〜3歳ごろがピークと言われています。
早ければ3歳前に落ち着く子もいますが、4歳を過ぎても“こだわり”が続く子も少なくありません。
これは性格や言葉の発達、家庭環境(下の子の誕生や保育園の変化など)によって大きく変わるため、“〇歳で終わらないとおかしい”ということは全くありません。
わが家の場合は、上の子(4歳)は3歳を過ぎたころにイヤイヤ期が落ち着きました。
当時は感情的になってしまうことも多く、今思えば「もっとゆったり構えられたらよかったな…」と後悔する場面もたくさんあります。
でもその経験があったからこそ、二人目ではイヤイヤ期すら「一緒に楽しむチャンス」と思えるようになりました。
イヤイヤ期は、子どもが心を育てる大切な時期。
だからこそ、子どもとの時間を意識して大事にするようにしています。
思いっきり遊んだり、話をじっくり聞いたり。
そうした関わりを重ねることで、信頼関係が深まり、イヤイヤ期も少しずつ乗り越えていける実感があります。
下の子(息子)はイヤイヤ真っ盛り中ですが、今回紹介した工夫で前よりずっとラクになりました。



終わるタイミングは子どもそれぞれ。
でも「心の土台作りの途中なんだな」と思えたら、見守る気持ちも変わってきますよ!
まとめ|子どもと向き合う力が育つ時期です
イヤイヤ期は、子どもが「自分ってなに?」「どう伝えたらいいの?」を一生懸命学んでいる時期。
それと同時に、私たち親も「どう関わるのがいいのかな?」と迷いながら、一緒に成長している最中です。
毎日うまくいくわけじゃないし、つい感情的になってしまう日もある。
でも、それでもいいんです。
完璧な親じゃなくて大丈夫。
大事なのは、「あなたと向き合いたい」って気持ちを、毎日少しずつ積み重ねていくこと。
たくさん笑って、ときに泣いて、イヤイヤ期も一緒に乗り越えていきましょう🌈
「今日もほんとによくがんばった!」って、まずは自分に言ってあげてくださいね☺️