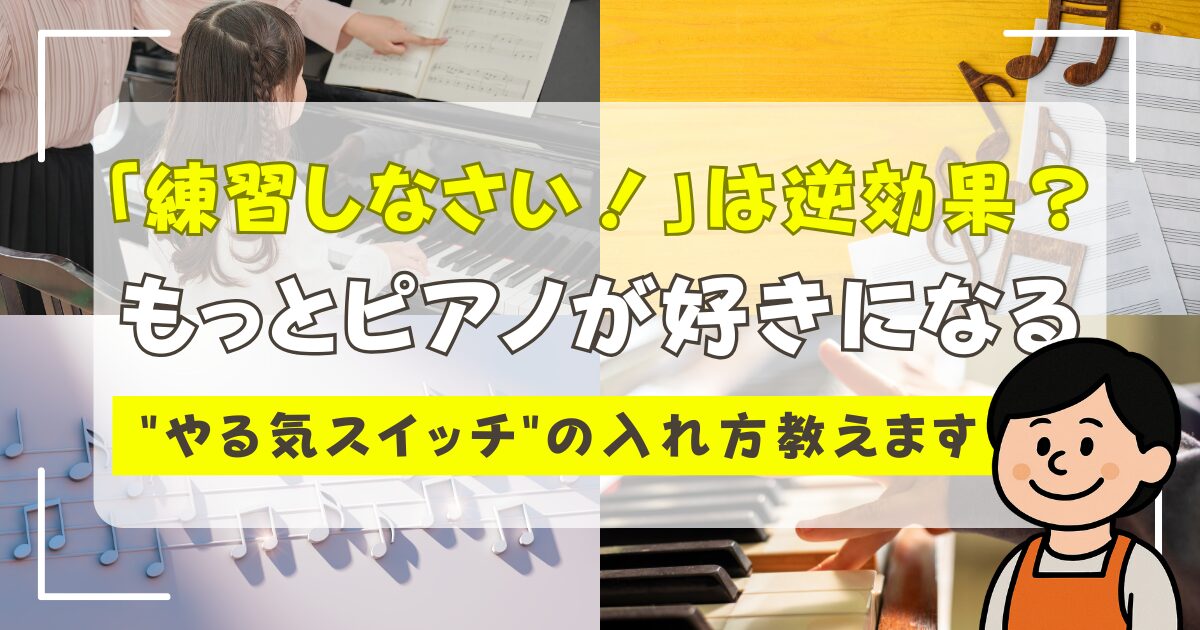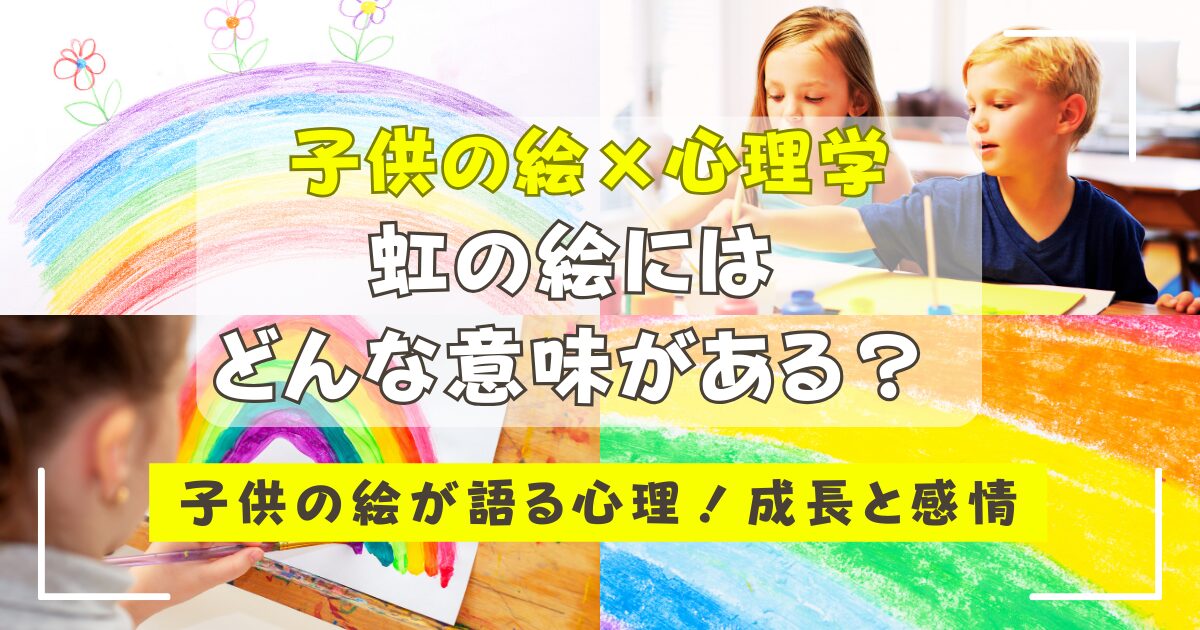「せっかく習ってるのに、全然練習しない」
「声をかければふてくされる」
「辞めたいとは言わないのに、ピアノから逃げるようになってる…」
そんなモヤモヤ、ありませんか?
今回は、小学生のピアノ練習にまつわる“あるあるお悩み”についてお話しします!
 なおみ先生
なおみ先生こんにちは、なおみ先生です🌷
保育士としての経験や、子育ての日々から感じたことをお届けしています。
よく聞くママたちの声…
「ピアノを習ってるのに、家で全然練習しないのよ」
「声かけすると不機嫌になって逆にやらなくなる…」
わかります、そのモヤモヤ。
せっかくお月謝払ってるし、上達してほしいって思っちゃいますよね。
でも実は、「練習しなさい!」の声かけが、逆効果になっているケースも。
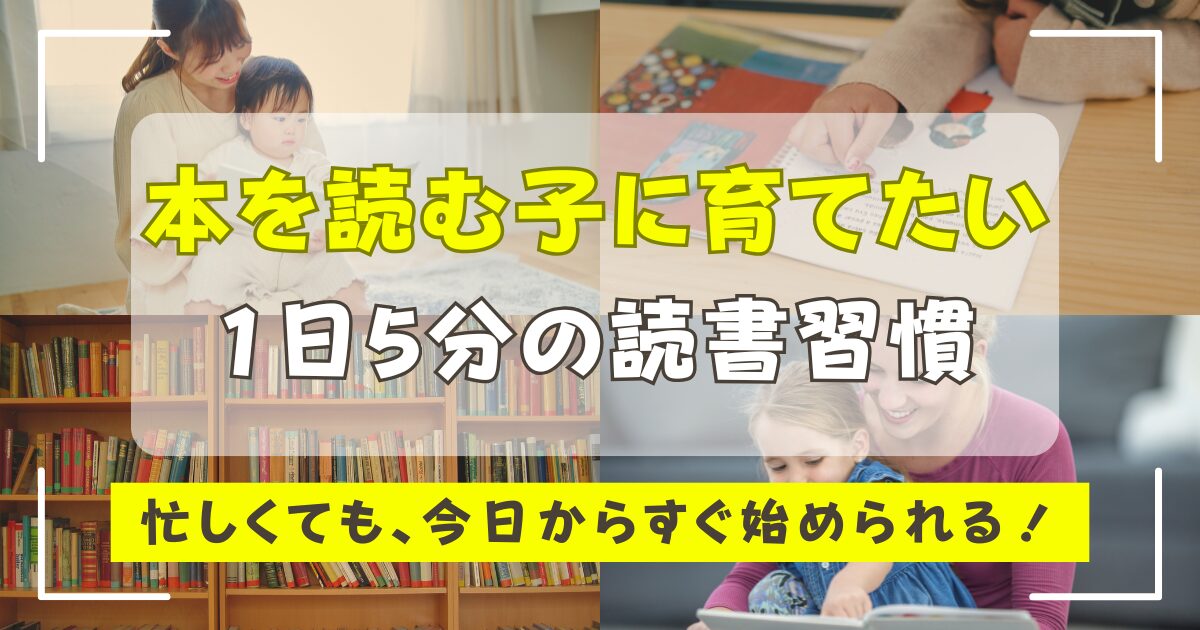
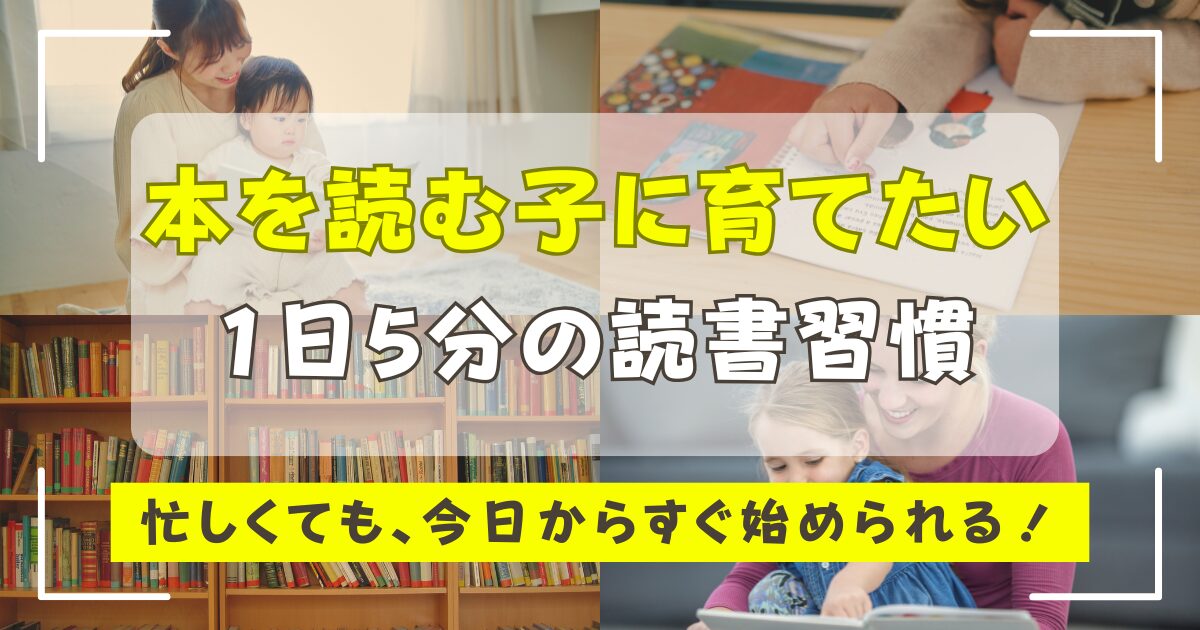
小学生がピアノを練習しない3つの理由
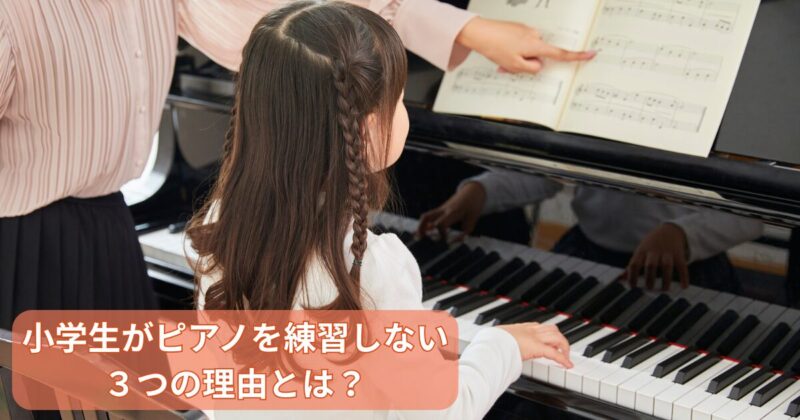
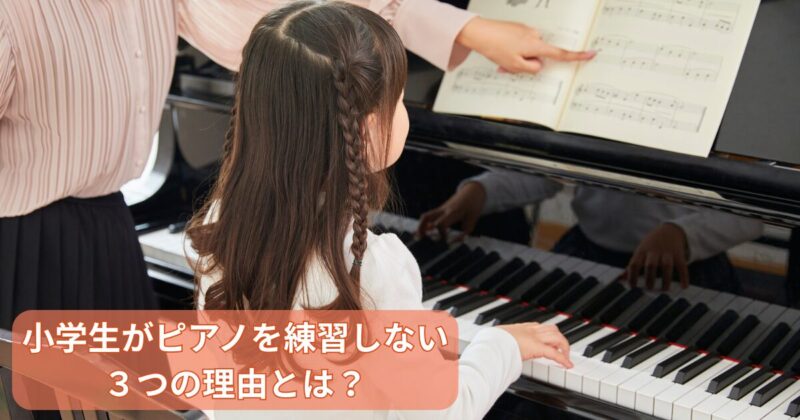
「上手くなる意味」がピンときていないから
小学生は、“今”を生きている存在。
「上手くなったら将来いいことがあるよ」
「続ければ上達するよ」
と言われても、
それがどれほど魅力的な未来か、想像しにくいんです。
こんな子ども像が思い当たりませんか?
- 「なんで練習しなきゃいけないの?」と純粋に不思議そう
- 楽譜よりもYouTubeやゲームに興味津々
- 発表会の予定が遠くて、気持ちが入らない



「この曲を弾いたらパパびっくりするかも!」という目の前の楽しみがあるほうが、断然やる気が湧きます。
「できない」が続いて、自信をなくしている
小学生の多くは、“頑張っているのに成果が出ない”ことにとても敏感です。
ピアノは間違いが音としてはっきり出るぶん、
「弾けない=自分は下手」と直結してしまいやすいんです。
こんなサインはありませんか?
- 練習中に「もう無理」「向いてない」などのネガティブ発言
- 間違えたときにふてくされる or 無言になる
- レッスンに行くのは平気なのに、家ではピアノに触れたがらない



この時期は、「できた!」の小さな達成感を積み重ねることがとにかく大切です。
なおみ先生の対処法:まずは「できる」を体験させてあげる
うちでも、最初は“楽譜が読めない”の壁に何度もつまずきました。
「この音なんて読むの?」「“レ”と“ミ”がわからない〜」と、毎回止まる…。
そんなとき、導入してみて本当に良かったのがぷっぷるのおんぷカード mini👇


- 可愛いイラストと色分けで、子どもが自分から楽しく使える!
- ト音記号もヘ音記号も網羅されていて、譜読みが早くなったとの声多数◎
- カルタ感覚・クイズ形式で“遊びながら覚えられる”と大好評
音符読みが苦手なお子さんにぴったりの、ヤマハ公式カード教材です♪
「ピアノ=怒られる場所」になっている
保護者にとっては「高い月謝」「時間のやりくり」…
つい期待やプレッシャーが大きくなってしまうもの。
でもその思いが、
「なんで練習しないの!」
「また間違えてるじゃん…」
など、無意識の圧になってしまうことも。
こうなっていませんか?
- 練習中の空気がピリピリしている
- 子どもが弾いていると、つい口を出したくなる(テンポ、強弱、指使いなど…)
- 練習中に泣いたり、すねたりすることが増えた
子どもは、ピアノそのものではなく「ピアノを練習しているときの家庭の空気」を感じ取っています。
怒られた経験が積み重なると、「ピアノ=イヤなもの」と脳が覚えてしまいます。
実は、私自身も子どもの頃ピアノを習っていました。
でも、家での練習時間は正直つらかった…。
「練習しなさい!」
「そこ違う!また間違えてる!」
「ちゃんと見てるの!?」
がんばって弾いても、返ってくるのはダメ出しばかり。
ほめられる前に直されて、「また怒られた…」という記憶ばかりが残ってしまいました。
それでも、「ピアノは嫌じゃない。好きになりたい」って気持ちはどこかにありました。



自信をもらえるような関わりがあったら、もっと楽しく続けられたのかな…と思うんです。
“一緒に喜ぶ関係”を大事にする
今、私は母親として子どもとピアノに向き合うとき、
「ダメ出しをしない」
「まず褒める」
「寄り添って一緒にやる」
を心がけています。
たとえ間違っても、
「おしい!でも、今の左手すっごく上手だったよ!」
「この部分、前よりスムーズに弾けるようになってる!」
そして、弾けなかった部分は
「1小節ずつ分けてやってみよっか♪」
「ママと交代でやってみる?」
と、小さな成功体験を一緒に重ねていくことを意識しています。
そんなふうに関わるようにしたら、子どもも「弾くの楽しい!」と感じるようになってきたんです🌷
小学生のピアノ練習に効く!やる気スイッチの入れ方5選【実践編】


「上手くなる喜び」より「好きな曲を弾ける楽しさ」にフォーカス
子どもにとって“練習=上達のため”はちょっと遠い話。
アニメソング、ゲームのBGM、家族のリクエストなら、本人の「弾いてみたい」がモチベに直結します。
ちなみに、最近うちの娘は、「ピタゴラスイッチ」の曲を弾くのにハマっています!
ピタゴラスイッチ→課題の曲という流れで楽しくすんなり練習するようになりました。
たとえばこんな工夫:
- アニメ・ゲーム・CMの曲を選ばせる(子どもの世界で「流行ってる曲」に興味津々!)
- 家族の誕生日に「この曲弾いてあげよう作戦」
- 「ママが好きな曲弾いて〜」とリクエストして、“お客さん”になる



「やらされている練習」ではなく、「誰かに聴かせたい」「自分が弾きたい」から弾く、という目的づけがカギです。
実際、わが家では【‘ヤマハ「ぷりんと楽譜」】を親子で愛用中!
アプリをタブレットに入れて画面で楽譜が見られるので、
紙の楽譜を印刷しなくてもよくて、めちゃくちゃラク!
- 1曲ずつダウンロード購入OK
- 初心者向けアレンジも充実
- J-POP、アニメ、ボカロ、クラシック…28万点以上の楽譜から選べる
- 月額480円〜のサブスクプランあり(初月無料!)
特にサブスクプラン「アプリで楽譜見放題」は、
毎月決まった数の楽譜を選んで閲覧できて、
うちの子は「今日はどれにしようかな♪」と曲選びから楽しんでます。
しかも、ママの私もちゃっかりお気に入りのJ-POP曲で練習してます…(笑)
\ 初月無料でお試し /
“毎日30分”はもう古い?1日3分の「スモール練習」戦略


子どもにとって「30分やりなさい」は、大人が思う以上に長い時間。
最初のハードルが高すぎると、「やる前から嫌」になりがちです。
1日3分だけでも“続けること”を目的にすれば、習慣化しやすくなります。
キッチンタイマーで「3分チャレンジ」にしてみるのもおすすめ。
わが家の場合は、習い始めの1年間は1日5分でしたが、
2年目の今は1日10分と自分でタイマーを設定して練習しています!
こんなふうに変えてみよう:
- キッチンタイマーで「3分チャレンジ!」→短いから取りかかりやすい
- 弾いた時間より「続いた日数」をカレンダーに記録→成功体験を積める
- 「今日は左手だけでいいよ〜」「1小節だけチャレンジ!」などミニ目標化



まずは“ピアノの前に座る”を習慣にする。継続が力に変わります!
操作がシンプルで子どもでも使いやすい!
音なし+光でお知らせできるので、静かな場所でも安心◎
大きくて見やすい表示と使い勝手の良さで、勉強や練習に大活躍✨
このタイマーをピアノの上にちょこんと置いて使っています♪
「練習しなさい」をやめて「聴かせて♥」に変える
「ママ、今日のあの曲もう一回聴きたいなぁ〜」と、観客ポジションになると、子どもの表情が変わります。
おすすめの声かけ:
- 「わあ!この前のとこ上手だったね。あそこもう一回お願いしていい?」
- 「今日の演奏タイム、そろそろですか〜?お客さん来てますよ〜(ぬいぐるみも並べる)」
- 練習の最後に「1曲だけ発表タイム」を設けて、家族みんなの拍手で締める👏



誰かのために弾く、見てもらえる、褒めてもらえることで、自信とやる気が育ちます。
「できた!」を可視化!シール作戦・記録ノートでやる気を目に見せる


子どもって、目に見える“ごほうび”が大好き。
カレンダーや専用の練習シートに「練習できたよシール」を貼るだけで、やる気に変わります。
わが家でも効果絶大だった“練習シールチャレンジ”!
子どもが張り切って「今日はシール何色にしよっかな〜♪」とノリノリに🎹✨
小さな達成感の積み重ねが、“練習=楽しい”に変わった瞬間でした。
おすすめのやり方:
- 練習した日=キャラ丸シール1枚(自分で選ばせると愛着◎)
- 10枚たまったら→ごほうびスペシャルシール!
- カレンダーや練習記録ノートに貼って、成長の可視化
+αで「1ヶ月続いたらごほうび」を設定してもOK!(例:好きな文房具、特別なおやつなど)



「努力=ちゃんと形になる」ことを体感させると、やる気が続きやすいです✨
ミスしてもOK!「間違い=成長のサイン」という安心感を伝える
「間違えてもいいよ」「今日はここまで弾けたね!」
大人が思っているよりも、子どもは“ミス=ダメ”と思い込んでます。
“できたところ”に注目して声かけすると◎
親の声かけで気持ちをラクにしてあげるのが一番。
こんな声かけがおすすめ:
- 「今日、すごくがんばってたね!間違えても練習してる証拠だよ」
- 「できなかったところ、あとで一緒に研究してみようか」
- 「ママも昔、発表会でミスしたよ〜(笑)でも楽しかったからOKだった!」



子どもにとって“失敗しても受け入れられる環境”は、チャレンジする力を育てます。
まとめ:やる気スイッチを育てよう
子どもは「やる気があるから練習する」わけじゃなくて、
やってみて楽しかったから、またやりたくなる。
そうして、“好き”が“得意”に変わっていきます。
焦らず、怒らず、
寄り添いながらスイッチを育てていけるといいですね♪